特許権で保護された先発医薬品の原薬を、ウェブサイトや展示会で宣伝することは許されるのか?
2025. 9. 10
特許権で保護された先発医薬品の原薬を、ウェブサイトや展示会で宣伝することは許されるのか?
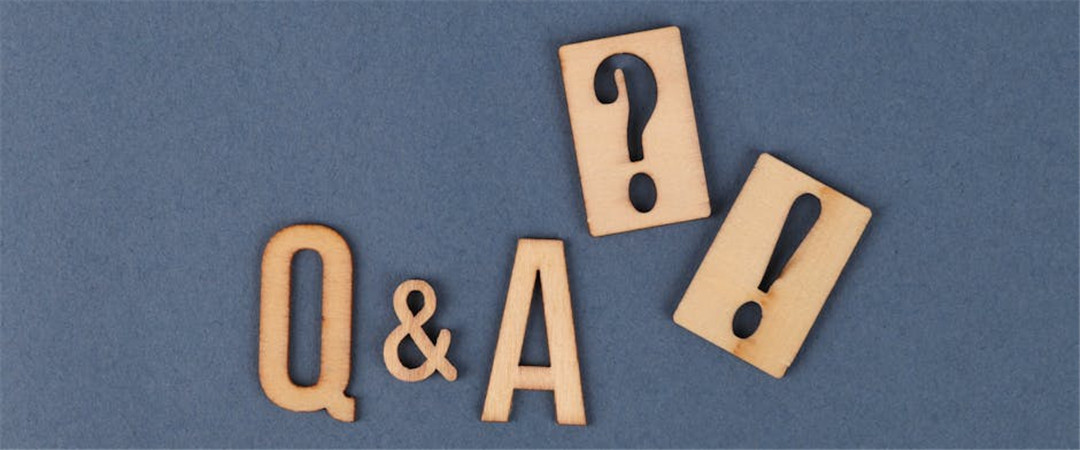
于佳佳弁護士
Q:特許権で保護された先発医薬品の原薬を、ウェブサイトや展示会で宣伝することは許されるのか?
A:この問題を検討するにあたり、以下の2つの事例が典型的な意義を有している。第一の事例における権利侵害企業は、上海の某医薬品と技術研究開発サービス会社で、自社のウェブサイトおよび展示会において、特許権で保護された先発医薬品の「ソラフェニブ(Sorafenib)」という抗がん剤原薬を展示したケースである。第二の事例における権利侵害企業は、南京の某製薬会社で、同じく自社のウェブサイトおよび展示会で、特許権で保護された「リバーロキサバン(Rivaroxaban)原薬」を展示したケースである。この両事例の処理結果は高い一致性があり、特許権者の許可を得ない原薬の展示行為は、特許法上の「販売の申出」に該当し、特許権侵害となり、また、医薬品の販売承認申請のための特許法上の例外規定(いわゆるBolar条項)の適用も認められないとされている。
まず、本件の行為が特許法に規定される無許諾の「販売の申出」に該当するか否かについて検討する。上海の会社は、製造販売目的での対象製品の販売はなく、展示行為は単に自社の研究開発能力と研究開発の方向性を示すものであり、販売の申出には当たらないと反論した。南京の会社は、その展示行為はリバーロキサバンのジェネリック医薬品の開発を計画している企業向けの限定的な情報提供であり、また対象製品はまだ販売できる条件が整っておらず、販売の申出には該当しないと主張した。しかし、これらの抗弁理由は認められていない。実際の販売がないことや販売能力がないことは「販売」を構成しないものの、特許法において「販売」と「販売の申出」は別個の権利侵害形態である。広告宣伝、商品陳列、ウェブサイトでの展示、或いは展示会での出展などの方法で製品販売の意思を表明する行為は、販売の申出と認定される。
次に、医薬品の行政承認審査における特許権侵害の例外規定(「Bolar例外」条項)の適用について検討する。特許法(2020年改正)第75条第5号によれば、行政承認審査に必要な情報を提供するための特許医薬品・医療機器の製造、使用、輸入、及びそれらを専らその目的のために製造、上述製品を輸入する行為は、特許権侵害とみなさないとされている。この条項の立法趣旨は、医薬品承認審査の時間的遅延問題の解決にある。仮に、ジェネリック医薬品企業が先発医薬品の特許期間満了を待って初めて試験や申請手続きを開始するとすれば、ジェネリック医薬品の実際の市場投入が特許権満了時期より大幅に遅延し、実質的に特許保護期間が延長されることになる。そこで、法律は特許保護期間中であっても、行政承認審査を目的とする特定の行為を認めている。本件において、上海の企業は、その展示行為は研究開発パートナーを探すためのものであると弁解し、製品は「R&D」研究開発段階及び「DMF」研究開発文書段階にあり、医薬品登録申請を行うための協力関係を求める必要があると主張した。南京の企業は、展示パネルに先発医薬品情報とBolar例外条項を明記していることを根拠に、その行為は行政承認審査の例外に該当すると主張した。医薬品の行政承認審査における特許権侵害の例外的な主体範囲には、「ジェネリック医薬品企業」及び「その試験を支援する第三者」が含まれており、両社とも自社は後者に該当すると主張している。しかし、この例外は「行政承認審査」目的の行為に限定されている。販売の申出という行為は明らかにこの一線を超えている。さらに、行政承認審査段階では、ジェネリック医薬品が最終的に承認されるか否かは不確実であり、事前の商業的宣伝は公衆を誤認させる可能性があるため、法律の定める例外事由には「販売の申出」行為は含まれない。
以上により、先発医薬品の特許権で保護された医薬品を、ウェブサイトや展示会で宣伝することは、特許権者の許可のない「販売の申出」に該当し、特許権侵害を構成することとなる。



