関連企業による複数事業労働者の場合、労働関係はどのように認定されるのか?
2025. 8. 20
関連企業による複数事業労働者の場合、労働関係はどのように認定されるのか?
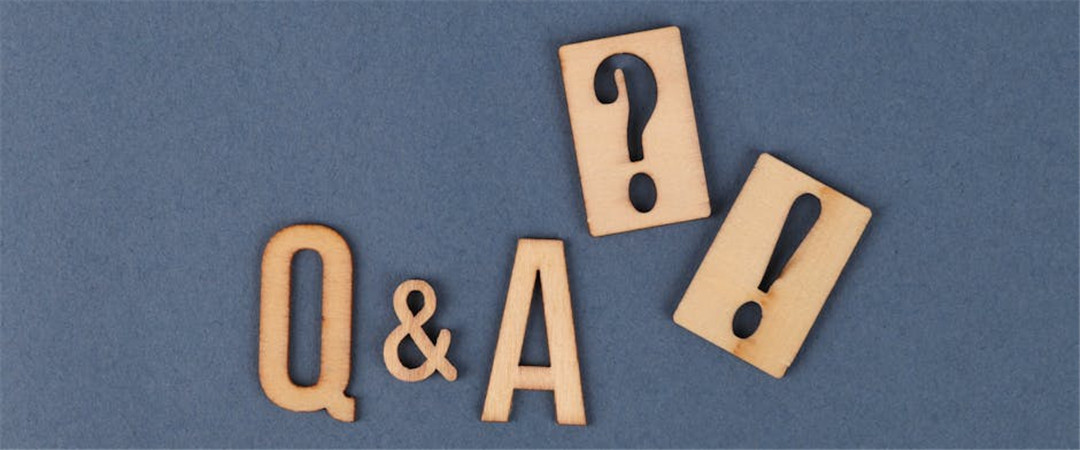
Q:関連企業による複数事業労働者の場合、労働関係はどのように認定されるのか?
A:「労働紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈(二)」(法釈〔2025〕12号)(2025年9月1日から施行)第三条において「労働者が複数の関連関係している企業に交替又は同時に使用され、労働関係の確認を請求する場合、人民法院は次に掲げる状況に応じて個別に処理すると規定している。
(一)書面による労働契約が締結されており、労働者が当該労働契約に基づき労働関係を確認することを請求する場合は、人民法院は法に基づきこれを支持する。
(二)書面による労働契約が締結されていない場合は、労働者雇用管理行為に基づき、勤務時間、業務内容、労働報酬の支払、社会保険料の納付等の要素を総合的に考慮して労働関係を認定する。
労働者が前条第(二)項の規定に該当する関連企業に労働報酬、福利厚生待遇等の支払について連帯責任を負うことを請求する場合、人民法院は法によりこれを支持する。ただし、関連企業間で労働者の労働報酬、福利待遇等について法に基づき約定を行い、かつ労働者の同意を得ている場合は、除外する」と規定している。
上述の規定に基づき、労働者が複数の関連関係している企業に交替又は同時に雇用される、すなわち関連企業による複数事業労働者が、既に書面による労働契約が締結されている場合は、労働者が当該労働契約に基づき労働関係の確認を請求する場合、労働契約に基づき労働関係を認定すべきである。関連企業のいずれとも労働者と書面による労働契約を締結していない場合は、労働者雇用管理行為に基づき、勤務時間、業務内容、労働報酬の支払、社会保険料の納付等の要素を総合的に考慮し、労働関係の主体を認定すべきである。また、書面による労働契約が締結されていない場合の責任主体については、労働者は複数の企業に連帯責任を負うことを請求することができるが、複数の企業間で労働者の労働報酬、福利待遇等に関して法に基づき約定を行い、かつ労働者がこれに同意すれば、連帯責任を負う必要はない。
さらに、「労働紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈(二)」(法釈〔2025〕12号)の発布会で(2025年8月1日)六つの典型事例が発布され、事例二は本条規定と関連している。当該事案において、審理法院は、某デジタル会社と某テクノロジ企業が関連企業に属し、事業内容には重複部分があり、梁氏が両社の株主かつ法定代表者を兼任しており、王氏には実際の雇用企業を判別することは容易でない。王氏はテクノロジ企業の名義によって招聘され入社したものの、勤務先には「某デジタル会社」のブランドで、業務上の連絡に使用された通信ソフトにも「某デジタル会社」の名称を冠にしており、王氏の業務内容には某デジタル会社の事業を含んでいたため、王氏がデジタル会社に使用されていると信じる相当な理由があると認定した。審理法院は判決で、王氏の某デジタル会社との労働関係の確認要求及び未払賃金の支払等の訴訟請求を支持した。
当方の提案:複数事業労働者と認定され、而して法的責任を負うことを回避するため、企業は労働者とタイムリーに書面による労働契約を締結し、賃金支払、社会保険の納付、労働者雇用管理の主体が労働契約の締結主体と一致していることを確保することに注意すべきである。労働者に複数の企業間の業務或いは作業を同時に処理させる必要がある場合は、複数の企業間で労働者の賃金報酬、福利厚生待遇、労働者雇用管理等の事項について明確に约定し、労働者の同意を得ることが望ましい。



