顧客情報は商業秘密に該当するか?
2025. 7. 29
顧客情報は商業秘密に該当するか?
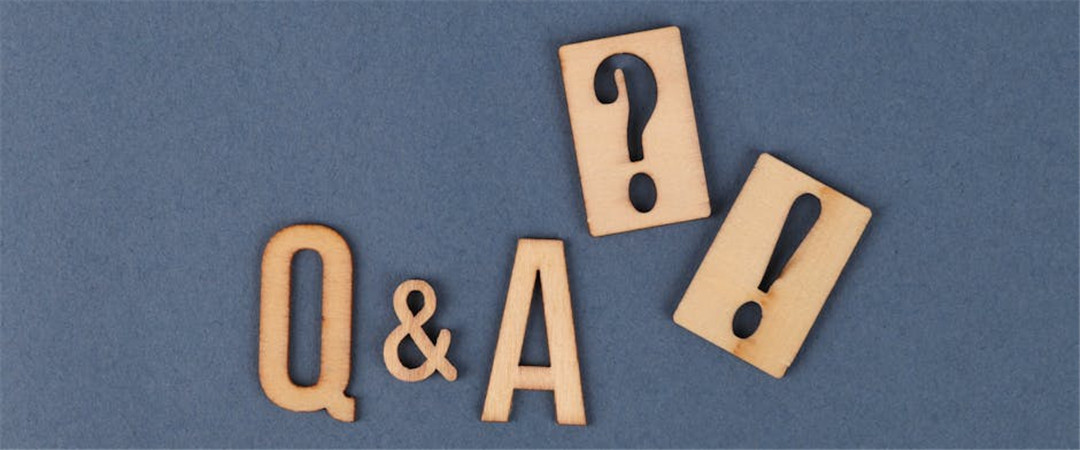
Q:顧客情報は商業秘密に該当するか?
A:「反不正当競争法」第9条第4項において、「本法において『商業秘密』とは、公衆に知られておらず、商業的価値を有し、かつ、権利者により秘密措置が講じられた技術情報や経営情報等の商業情報を指す」と規定されている。「最高人民法院による商業秘密侵害民事事件の審理に関する法律適用の若干の問題についての規定」において、次のように更に明確化された。「経営活動に関連する創意、管理、販売、財務、計画、サンプル、入札資料、顧客情報、データ等の情報は、人民法院が反不正競争法第9条第4項に規定している『経営情報』に該当すると認定し得る。」「前項に規定している顧客情報には、顧客の名称、住所、連絡方式及び取引習慣、意向、内容等の情報が含まれる。」
ゆえに、商業秘密は顧客情報を含み得るものの、全ての顧客情報が必ずしも商業秘密に該当するわけではない。法的要件を満たす顧客情報に限り、商業秘密として認められ、法律による保護の対象となる。
商業秘密に該当する顧客情報の認定について、法答網(最高人民法院が全国の四段階の法院職員に、法律政策の運用、裁判業務に関する相談・回答および学習交流サービスを提供する情報共有のプラットフォーム)の精選Q&A(第二弾)において、次のような権威的かつ詳細な回答が掲載されている。「顧客情報は主に二つの部分から構成される。一つは顧客の名称、住所、連絡先などの情報、すなわち基本情報である。もう一つは取引習慣、意向、価格受容力などの情報、すなわち深度情報である。ただし、この分類は顧客情報が商業秘密に該当するかどうかの認定に必然的な影響を及ぼすものではない。顧客情報が商業秘密に該当すると判断する基準は、法律に規定された『公衆に知られておらず、商業的価値を有し、かつ権利者により秘密措置が講じられている』、すなわち秘密性、価値性、機密性を満たしているかどうかによる。(以下省略)」
最高人民法院案例庫に登録された事例(登録番号:2023-09-2-176-013)において、一般的な商業情報の商業秘密に該当する認定規則について具体的な解釈が述べられた。当該事例において、被告の譚氏はA社退職後、A社勤務中に取得した、かつA社より秘密管理措置が講じられた顧客リスト及び取引意向等の商業情報を、新たに勤務先となったB社(同被告)に数回も漏えいし、不正に利用した。両被告ともに当該行為により利益を得た。人民法院は審理を経て、譚氏及びB社がA社の商業秘密を侵害していることを認定した。人民法院は本件の顧客情報について、以下のような定性分析を行った。
1. A社が保有する顧客情報には、顧客の名称や電話番号などの基本情報のほか、取引意向やニーズなどの情報も含まれている。特に、当該取引意向及びニーズには、工商登記手続代行、営業許可証取得代行、記帳代行、納税申告代行のほか、引き合い、見積もり、成約価格等の即時性・秘密性を有し、現実的な利益をもたらし得る商業情報が含まれており、商業秘密として保護されるべきものとして認められた。
2. 両被告がA社の顧客情報を交換・売買し、それにより利益を分配した行為は、当該商業情報が一定の商業的価値を有することを示している。それに、被告の譚氏は労働契約においてA社の商業秘密を保持することを約束したことから、A社は当該商業秘密に対して適切な秘密保持措置を講じていたことが明らかになった。
上記に基づき、譚氏が保有していたA社の顧客情報は商業秘密に該当し、譚氏及びB社がA社の顧客情報を不正利用して利益を得た行為に対し、A社の経済的損失に対する懲罰的超過賠償を命ずるべきであった。
実務上、顧客情報に関わる商業秘密侵害をめぐる不正競争紛争は、従業員の退職後に頻発する傾向がある。例えば、元従業員が顧客情報を不正利用して同種業務に従事し、企業に多数の顧客流失をもたらす事案が多く見られる。このような場合、企業は当該顧客情報が商業秘密に該当することを理由として、退職した従業員等が関連する民事主体を相手取り、商業秘密侵害による差止請求及び損害賠償請求を提起することが多い。このような紛争は頻発するものの、前述の通り、「秘密性」、「機密性」、「価値性」という3つの要件を同時に満たす場合にのみ、商業秘密として認定される。



