株式譲渡は善意取得の制度を適用できるか?
2025. 9. 23
株式譲渡は善意取得の制度を適用できるか?
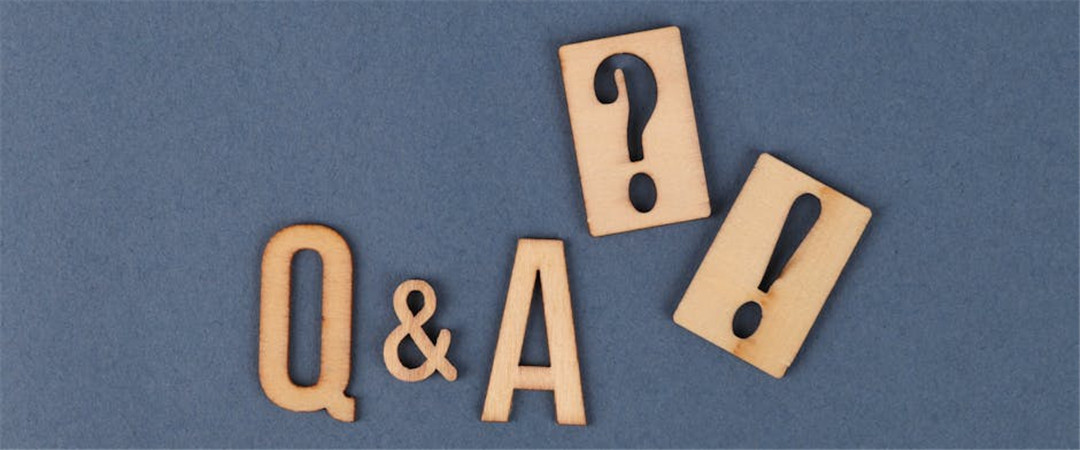
Q:株式譲渡は善意取得の制度を適用できるか?
A:適用できる。「『中華人民共和国会社法』の若干の問題の適用に係わる最高人民法院の規定(三)」第25条第①項の規定によれば、名義上の株主が自己の名義に登記されている株式を譲渡、質権設定その他の方法で処分した場合、実際の出資者が当該株式に対して実質的な権利を有することを理由として、株式処分行為の無効を請求したときは、人民法院は「民法典」第311条の規定を参照して処理することができる。
民法典第311条の規定と合わせて考慮すると、株式譲渡に善意取得を適用するには、以下の条件を満たす必要がある。
1. 譲受人が当該不動産又は動産を譲り受けた時に善意であること。すなわち、株式の譲受人が名義上の株主と実際の出資者間に株式代持関係が存在することを知りながら、実際の出資者の同意を取得しなかった場合、譲受人は善意取得に該当しない。
2. 合理的な価格で譲渡されていること。つまり、株式譲渡の価格は相場に符合し、著しく高額又は低額ではないこと。
3. 譲渡された不動産又は動産が法律の規定により登記すべきものであるときは既に登記が完了しており、登記を要しないものであるときは既に譲受人に引き渡されていること。これは、株式が未だ移転していない段階においては、匿名株主(実際の出資者)が株式譲受人に対し権利を主張できること、元の株式譲渡契約は履行を継続できないことを意味する。同時に、株式譲受人は名義上の株主(譲渡人)に対し損害賠償を主張することができる。しかし、株式の移転が完了した後は、匿名株主は当該株式を回復することはできず、代持契約の定めに基づき、名義上の株主の責任を追及することのみ可能となる。
株式譲渡の過程において、譲受側は十分な評価調査を実施し、名義上の株主による無断譲渡等の状況が発生することを極力回避すべきである。また、実際の出資者について言えば、専門家の指導の下で株式代持のスキームを合理的に設計し、名義上の株主の権利義務に対して明確な約定を行い、将来発生し得るリスクを低減するようご注意ください。




